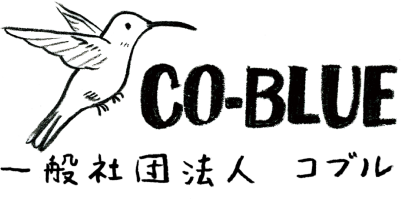ひきこもりで悩んでいるご両親との面談ではよく「自分から動き出してほしい」という願いを話されるのを聞きます。
確かになんでも人任せ、自分で考えられない、選べない、では、自分達がいなくなった後のことを思って「この子は一人でも生きていけるのだろうか」と心配になるのも当然です。
自分から動き出す=「自主性」というのは「ひきこもり」という場面においては矛盾を抱えている面があります。
それは「自分のことなんだから、自分で動き出さなきゃ」と自主性を持つことの必要性を親が当事者に訴えた時点で、すでに自主性がないということです。
その言葉を聞いて自分から動いた場合、「親から自主性を持てといわれたので動いた」わけですから自主性があるとはいえないわけですし、かといって何もいわずにいると「いつになったら自分から動き出すんだ」となって心配は募るばかり。
この矛盾から脱するには視点を変えることが必要なんだと思います。
それは「自分から動き出してほしい」という自主性ではなく、「自分で決めてほしい」という自己決定、という視点を持つということです。
親としてひきこもりである子供が自己決定することを、どうサポートするかを考えてみるのはいかがでしょうか。
その自己決定の結果は親が望むものではない場合もあり得ます。例えば、就労を選ばないこともあり得るということです。
でも自己決定をサポートした場合には、結果として就労や社会参加を選ぶことがほとんどです。仮に就労や社会参加を選ばなかったとしても、生活していくために必要な福祉制度などの利用を了承されることがあります。
2025年1月に厚生労働省から発表された「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」はまさにこの自己決定を「自律」という大切な価値観として扱っています。
「自己決定」については同じく厚生労働省の「意思決定支援の基本的考え方〜だれもが「私の人生の主人公は、私」〜」というわかりやすいパンフレットで説明されています。
どちらもぜひご一読いただきたいです。
といっても実際には教科書通りにはいかないというか、ひきこもっている当事者にも考えをあらためてもらわないと前に進まないことがあるというか、同じくご両親や同居する親族にも考えをあらためてもらわないと前に進まないことがあるというか、支援者側も考えをあらためないと前に進まないことがあるというか。
みんな自分の想いや考えがあり、それが教科書通りの想いや考えとの間にジレンマを起こし、悶々として日々を過ごしているというのが、僕も含めて実際のところなんじゃないのかなぁと思ったりしています。